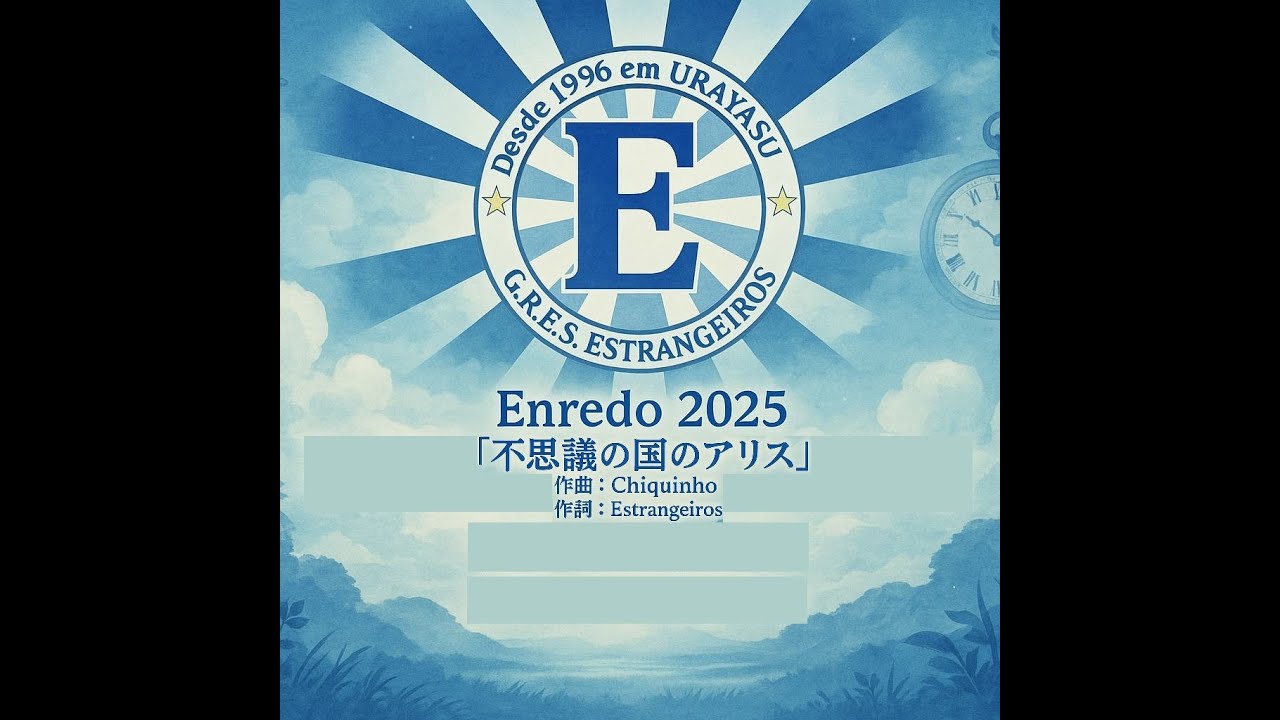検索結果
空の検索で30件の結果が見つかりました。
- 第40回(2025年)浅草サンバカーニバル・パレード動画まとめ
第40回浅草サンバカーニバルのパレード本番動画をS1リーグ・S2リーグまとめて公開します! 撮影・協力:ジンガブラジル 山本リオさん(YouTubeチャンネル: Rio SAMBA-浅草サンバカーニバル- ) 各チームの出場回数、活動拠点などプロフィールなどは浅 草サンバカーニバル公式サイト もご参照ください。 <S1リーグ> 優勝:サウーヂ 準優勝・アサヒビール特別賞:ウニアン 3位・アレゴリア賞:バルバロス 4位:グローリア 5位:アレグリア 6位:リベルダージ ◼︎S1/S2リーグ得点表(各審査項目の定義は記事の下部に記載) サウーヂ〜リベルダージがS1リーグ、インペリオ〜フェスタンサがS2リーグ テーマの表現 躍動感 衣装 演奏 ダンス 総合評価 合計 サウーヂ 55.0 55.0 55.0 55.0 56.0 75.0 351.0 ウニアン 54.0 58.0 52.0 56.0 54.0 75.0 349.0 バルバロス 55.0 54.0 55.0 53.0 56.0 75.0 348.0 グローリア 51.0 49.0 49.0 49.0 49.0 65.0 312.0 アレグリア 51.0 51.0 49.0 49.0 47.0 68.0 305.0 リベルダージ 48.0 48.0 48.0 46.0 49.0 63.0 302.0 インペリオ 44.0 45.0 47.0 46.0 47.0 68.0 297.0 アミーゴス 45.0 46.0 45.0 47.0 46.0 64.0 293.0 セレージャ 39.0 45.0 47.0 45.0 44.0 59.0 279.0 アハスタォン 37.0 40.0 39.0 39.0 33.0 56.0 244.0 エストランジェイロス 37.0 35.0 38.0 32.0 33.0 51.0 226.0 フェスタンサ 32.0 32.0 30.0 32.0 28.0 44.0 198.0 <S2リーグ> 優勝:インペリオ 準優勝:アミーゴス 3位:セレージャ 4位:アハスタォン 5位:エストランジェイロス 6位:フェスタンサ ◼︎浅草サンバカーニバルの審査基準( 浅草サンバカーニバル公式サイトから引用 ) 審査項目(6項目)および各項目の審査基準は以下のとおりです。 ①テーマの表現 アーラ(チーム内の小グループ)、アレゴリア(フロート含む)等のパレード構成がテーマを表現しているかを評価します。 ②躍動感 サンバ・ジ・エンヘード(パレードのテーマ曲)に合わせたグループ全体の盛り上がり・躍動感を評価します。 また、その盛り上がりが観客にも伝わっているかどうかを評価します。 ③衣装 テーマに沿った表現・デザインができているかを評価します。 衣装の色のバランスやデザインセンスを評価します。 ④演奏 サンバ・ジ・エンヘードの、楽曲としての評価を行います。 パレードにおける打楽器、歌、弦など演奏全体の総合的な評価を行います。 ⑤ダンス テーマに沿った表現をしているかを評価します。 サンバにあわせた動きになっているか、元気があるかなどを評価します。 ⑥総合評価 演奏、ダンス、衣装、アレゴリア(フロート含む)を含むパレード総体の評価を行います。 隊列が滞りなく進行しているかについて評価します。 審査員は専門審査員(全項目を審査)8名と特別審査員(総合評価1項目のみ)2名で構成されます。 審査は各項目10点満点、リオ形式と同様で専門審査員8名の最上位点と最下位点各1名を除外して、各項目ごと、中間6名の合計60点満点での採点(総合得点は380点満点)とし、1点単位での審査とします。 S1リーグについて、次の3要素を満たしていないチームについては総合得点から減点を行います。 これは浅草サンバカーニバルが目指す「リオのカーニバル」に近づくため、これらの要素の充実を図る目的で行うものです。出場の必須条件ではありませんが、是非パレードに取り入れられますようご協力下さい。 減点対象となる要素は、 ①コミサン・ジ・フレンチ(注1) ②ポルタ・バンデイラ/メストレ・サラ(注2) ③バイアーナ(4名以上)(注3) の3要素です。 これらの要素が欠けている場合には、1要素につき10点ずつ総合得点から減点をします。 これらの要素が満たされているかどうかは事前に各チームから申告いただいた上で、当日実行委員会事務局が判断し、減点については審査員の了承の上決定します。 (注1)隊列の先頭に位置し、テーマを直接・間接に提示するアーラ(小グループ) (注2)チームの旗を持つ女性と、それを守る男性による二人のペア (注3)バイーア地方の特徴を有する大きなフレア状のスカートを中心とした衣装による4名以上の女性のアーラ(グループ) 浅草サンバカーニバルパレードコンテンストに参加されたチームの皆様、酷暑の中本当にお疲れ様でした!
- 第40回(2025年)浅草サンバカーニバル審査結果
2025年8月30日に開催された、第40回浅草サンバカーニバルの結果をお知らせします。 👑S1リーグ優勝 エスコーラ・ヂ・サンバ・サウーヂ 🎉S1リーグ準優勝&アサヒビール特別賞 学生サンバ連合 ウニアン・ドス・アマドーリス 🎖️ S1リーグ3位&アレゴリア賞 G.R.E.S. 仲見世バルバロス 🏆S2リーグ優勝 インペリオ・ド・サンバ 🥈S2リーグ準優勝 アミーゴス・カリエンテス 🥉S2リーグ3位 フロール・ヂ・マツド・セレージャ 受賞されたチームの皆さん、おめでとうございます! ▼審査結果はこちら https://www.asakusa-samba.org/wp-content/uploads/2025/08/judge40_20250830.pdf 写真提供: 浅草サンバカーニバル実行委員会
- 2025浅草サンバカーニバル「アハスタォン」のテーマ&楽曲を紹介
ブロコ・アハスタォン https://www.arrastao.com/ テーマ: (間)違い探し ~自分らしさを大切に、まわりと違っても大丈夫~ サンバ・ヂ・エンヘード: https://arrastao.com/2025/Enredo%202025.m4a シノプス: 各アーラに、間違いがひとつあります。 沿道の皆さん、報道の皆様も、 間違いを見つけてくださいね。 でも、 間違いに見えるようで、間違いではないのです。 歌詞: アレ?アレ?アレ? 間違い探し 間違いに見えるけど 間違いじゃない ALLEZ!! ALLEZ!! ALLEZ!! 間違いじゃない いろいろ色があるから虹が美しい よく見てごらん かわっている所があるから いくつの間違い 見つかるでしょう 5月の空を 飛ぶ鯉のぼり 恋をしたなら 天まで飛ぶだろう 急に降ったら雨合羽 きゅうり食ったら 皿カッパー 海のメイドはマーメイド サンバのセールはマルメラアダ 飛び上るチアガール 盛り上がるビアガール それにつけても おやつはカール
- 2025浅草サンバカーニバル「エストランジェイロス」のテーマ&楽曲を紹介
G.R.E.S. Estrangeiros(エストランジェイロス) http://estrangeiros.jp/ テーマ:「不思議の国のアリス」 サンバ・ヂ・エンヘード: シノプス: 歌詞: ※【サビ】※ 歌え!踊れ! so Estrangeiros! 心のまま 今はただ(Sega seu coracao シガ セウ コラサォン) 時が経つのも忘れたままで 熱いBATIDAを感じて 歌え!踊れ! so Estrangeiros! 今日は明日じゃ満たされない(Nao satisfeito ナォン サティスフェイト) そう、人生は いつもCALNAVAL! 今この瞬間(とき)燃えて 輝いて 【Aメロ】 ねぇ 目を閉じてみて(Oh~Oh~Oh~)※最後の〆だけ【さぁ 目を開けてみて~】 深く息をして(Oh~Oh~Oh~) 飛び込もう! 不思議の国 広がる自由な世界 Alice no pais das maravilhas(アリス ノ パイス ダス マラヴィーリャス) 【Bメロ】 進む道 迷うとき 何を信じればいいか 悩むとき そんな時には (YEAH!) ホーダde(で)ティーパーティー! 【Cメロ】 一緒に祝おう!なんでもない日を・・・(なんでもない日おめでとう!) (SAUDE!)泣いて 笑って 盛り上がれ! 頭からっぽにして Sambaで満たそう!なんでもない日を・・・(なんでもない日おめでとう!) (SAUDADE!)同じ日は二度とない Especial todos os dias(エスペーシャウ トードス オス ヂーアス) ※繰り返し
- 2025浅草サンバカーニバル「リベルダージ」のテーマ&楽曲を紹介
G.R.E.S. LIBERDADE(リベルダージ) http://www.gres-liberdade.com/wordpress/ テーマ:「夏っ!」 サンバ・ヂ・エンヘード: シノプス: 歌詞: 夏っ! 日常からの解放 Liberdade! 作詞:キーナ ニチーニョ 作曲:ニチーニョ Que calor ! Que calor ! Que calor ! 暑い夏 Que calor ! Que calor ! Que calor ! 夏 今年も今年も今年もアツい日が また来るから 行こうよ 太陽がすべてを彩るカルナヴァウ! 太陽に向かってCarnaval ! ひかり輝き 街中の熱気 誰もみな 無敵になる 自由を彩り より鮮やかに 日常からの解放 Liberdade! 強烈な日差しが照り付ける 熱い体 冷やしてほしい 花火がドカーン 夏が来た 冷たいフルーツ 冷えたビール 熱い体 冷やしてほしい サンバでドカーン 夏が来た 土の中で 力貯めて 生きてきたものが 顔を出す そしてまた 陽が昇る あらたな夏の1日が始まる
- 2025浅草サンバカーニバル「アミーゴス」のテーマ&楽曲を紹介
アミーゴス・カリエンテス https://amigoscalientes.jp/ テーマ:「春夏秋冬」〜四季折々の宴とリズム〜 サンバ・ヂ・エンヘード: http://amigoscalientes.jp/upload/up/Syunkasyutohshikioriorinoutgagetorithm128k.mp3 シノプス: 舞台は日本、彩り豊かな四季を旅する祝祭の物語。 桜舞う春は、希望に満ちた仲間との語らい。 太陽と海が照らす夏は、笑顔と太鼓が響く命の輝き。 収穫の秋は、月明かりと共に語り合う静かな喜び。 そして、銀色に染まる冬は、新しい季節を迎える乾杯のとき。 それぞれの季節が描き出すのは、人々の笑顔とリズムが溶け合う「宴」。 グラスを交わし、歌い、踊るのは、サンバを愛する仲間たち──Amigos Calientes。 さあ、バンデイラを高く掲げよう。 春夏秋冬を彩る祝祭のリズムが、今ここに響き渡る。 日本の四季に導かれた、Amigosの物語をお楽しみください。 歌詞:
- 児童のサンバパレード参加に関する見解
※2022年にAESA内で議論して出した声明文を改めて掲載いたします。 以前、小さな女の子が露出の多い過激な衣装でサンバを踊っている写真がネット上で話題となりました。 寄せられた意見の多くは、小さな子どもに露出の多い衣装を着せていることについて、サンバチームの見識を問うものでした。それらの写真は浅草サンバカーニバル及びAESA加盟チームのものではありませんでしたが、私たちは日本のサンバ界全体の問題として捉え、加盟チームの評議員会議で話し合いを持ちました。 私たちAESAの思いや願いを、見解としてまとめましたので、親愛なるすべてのサンビスタの仲間と、いつも応援してくださる皆さんにご報告いたします。皆さんのご理解を賜りますよう、お願いいたします。 浅草エスコーラ・ヂ・サンバ協会(AESA) ================= 児童のサンバパレード参加に関する、AESAの見解 2022年9月29日 浅草エスコーラ・ヂ・サンバ協会(AESA)加盟チーム一同 私たち「浅草エスコーラ・ヂ・サンバ協会(AESA)」は、浅草サンバカーニバルのS1リーグに所属か、所属経験のあるサンバチームのうち、協会の趣旨に賛同する11チームが加盟する協会です。浅草サンバカーニバルの発展と、加盟チームの交流・親睦のために活動しています。 露出の多い衣装を着た子どもがサンバパレードに参加している写真が、ネット上で問題となっています。小さなお子さんが自分で衣装を選んでいるとは思えず、親や周囲の大人たちが進んで過激な衣装を着せているものと思われます。サンバチームの側から見て大変残念な行為です。子どもにセクシーな衣装を着せていることについて、サンバチームの見識を問う意見がネット上にあがっています。この件について、協会で話し合いを行いました。 私たちAESA所属のサンバチームは、ブラジルの文化であるサンバの楽しさと魅力を広げていきたい、どなたにもサンバを楽しんでいただきたいと願い活動しています。その点で、一部のサンバチームのこのような行為は私たちAESAの願いとは無縁なものであり、大変残念なことだと考えています。 日本では女性ダンサーの衣装が話題となりがちですが、サンバの魅力はそれだけではありません。小さなお子さんが着るのに相応しくない、過激な衣装を着せて注目を集める行為は、観る人にサンバに対する誤解を与えます。サンバパレード本来の姿、本当に見て欲しいもの、聴いて欲しい音を伝えたいという私たちの願いとは無縁なものです。 私たちは、様々な場所でサンバを披露し、多くの皆様に楽しんでいただいています。どなたにも気持ちよくサンバを楽しんでいただくためには、観る人が不快に感じることや公序良俗に反することは、やってはいけないと考えています。 小さな子ども達は、私たち大人がみんなで守るべき存在です。しかし、子どもに露出の多い衣装を着せて大勢の前に出すことは、子どもの人権を侵害することにつながりかねません。大人たちはその点に留意して、こども達に配慮しなければなりません。 私たちは、大勢の皆様に応援いただいていることに感謝しています。皆様にサンバ本来の魅力を伝え、気持ちよく楽しんでいただくことは、私たちの喜びでもあります。私たちは、全てのサンバチームから今回問題となったような行為がなくなるように努力していくことを肝に銘じ、今後もサンバの楽しさ、魅力を多くの人に伝えるために活動してまいりますので、引き続きの応援をどうかよろしくお願いいたします。
- 第40回(2025年)浅草サンバカーニバル各チームのテーマ&楽曲を公開!
2025年8月30日、第40回浅草サンバカーニバルが開催されます。 各チームのパレードにはオリジナルのテーマ、ストーリー(シノプス)、楽曲(サンバ・ヂ・エンヘード)があります。カーニバル本番の前に予習していけば、楽しさが10倍に増えるのは間違いなしです!ぜひご覧ください。 <S1リーグ> バルバロス https://www.aesa.jp/post/2025barbaros-enredo サウーヂ https://www.aesa.jp/post/2025saude-enredo ウニアン https://www.aesa.jp/post/2025uniao-enredo アレグリア https://www.aesa.jp/post/2025alegria-enredo リベルダージ https://www.aesa.jp/post/2025liberdade-enredo グローリア https://www.aesa.jp/post/2025gloria-enredo <S2リーグ> セレージャ https://www.aesa.jp/post/2025cereja-enredo アミーゴス https://www.aesa.jp/post/2025amigos-enredo インペリオ https://www.aesa.jp/post/2025imperio-enredo アハスタォン https://www.aesa.jp/post/2025arrastao-enredo エストランジェイロス https://www.aesa.jp/post/2025estrangeiros-enredo フェスタンサ https://www.aesa.jp/post/2025festanca-enredo
- 2025浅草サンバカーニバル「フェスタンサ」のテーマ&楽曲を紹介
G.R.E.S. FESTANÇA(フェスタンサ) テーマ:新たなる飛翔 サンバ・ヂ・エンヘード: シノプス: ブラジルのジャングルをさまよっていたフェスタンサ探検隊。 幸運の鳥に導かれて新たな旅へと出発! そこで出会ったのは色とりどりの美しい鳥たちと サンバのリズムを奏でるトゥッカーノたち。 2024年は残念ながら出場を見送ったフェスタンサですが 今年新たな仲間とともに、お祭り騒ぎを繰り広げます! 歌詞: ASAS MARAVILHOSAS, EM TODO SEU ESPLENDOR, RUMO AO CÉU SUPERIOR G.R.E.S. Festança Na alegria da Festança Acordei toda a cidade Quando em Verde e Laranja Encontrei felicidade… Alo Festança!! A hora e essa… Sai da frente!! Vindo pelas mãos do Criador (Oba!!) A Natureza está aqui pra desfilar No seu esplendor... Trazendo Aves, com vontade de brincar E a Festança, numa mesma direção Vem pra avenida encantar a multidão Fênix do amor Batendo asas foi ao Céu Superior Olha o Uirapuru da sorte Coração é quem me diz No balanço do meu samba Minha vida é mais feliz Oxum, Minha Mãe, na beira do rio Ogum, O Guerreiro, num sonho surgiu O Cisne Branco se glorificou E a proteção de Deus abençoou Martin-Pescador, o Pica-Pau e o Gavião Tem João de Barro, Tuiuiú e o Azulão Ouço as Araras-Canindé a gorjear De uma Coruja não se pode duvidar Vem o Tucano exalando energia Com a nossa bateria ! É meu orgulho, minha liberdade Verde e Laranja, traz a alegria Hoje a Festança é só felicidade A Campeã no Reino da Folia... É campeã!!!!!!!!!!!!!!!!! (日本語訳) ASAS MARAVILHOSAS, EM TODO SEU ESPLENDOR, RUMO AO CÉU SUPERIOR 素晴らしい翼、そのすべての輝きはより高い空へ向かう G.R.E.S. Festança Na alegria da Festança Acordei toda a cidade Quando em Verde e Laranja Encontrei felicidade… フェスタンサの喜びの中、わたしはすべての街を目覚めさせた 緑とオレンジの時、幸福に出会った(※緑とオレンジ=フェスタンサのこと) Alo Festança!! A hora e essa… Sai da frente!! ハロー フェスタンサ!時間がきたよ。さぁ前に出よう! Vindo pelas mãos do Criador (Oba!!) A Natureza está aqui pra desfilar No seu esplendor... Trazendo Aves, com vontade de brincar 創造の神の手から創られた すべての自然はパレードのために、光の輝きの中、ここにいる 鳥たちがカーニバルで遊びに来ている E a Festança, numa mesma direção Vem pra avenida encantar a multidão Fênix do amor Batendo asas foi ao Céu Superior フェスタンサは同じところにいる 観衆を惹きつけるためにアベニーダにやって来た 愛のフェニックス 翼を打ち、空高くへ舞った Olha o Uirapuru da sorte Coração é quem me diz No balanço do meu samba Minha vida é mais feliz 幸せのウイラプルを見てごらん コラソンは、誰が言ったのだろう? 私のサンバの揺れ(スウィング)の中で 私の生命(人生)はもっともっと幸せだ Oxum, Minha Mãe, na beira do rio Ogum, O Guerreiro, num sonho surgiu O Cisne Branco se glorificou E a proteção de Deus abençoou オシュン、川にいる私たちの母 オグン、軍神、夢で現れた 白鳥達が賛美し、 神が加護した Martin-Pescador, o Pica-Pau e o Gavião Tem João de Barro, Tuiuiú e o Azulão マーチンぺスカドール、キツツキ、ワシ ジョンジバッホ、ツイウイウ、アズラォンがいる Ouço as Araras-Canindé a gorjear De uma Coruja não se pode duvidar Vem o Tucano exalando energia Com a nossa bateria ! インコのさえずりが聞こえる フクロウは悪い前兆 エネルギーを広げツゥッカーノが来る 私たちのバテリアと共に É meu orgulho, minha liberdade Verde e Laranja, traz a alegria Hoje a Festança é só felicidade A Campeã no Reino da Folia... É campeã!!!!!!!!!!!!!!!!! 誇り、自由 緑とオレンジ、喜びを連れてくる 今日、フェスタンサは幸福しかない お祭りの国のチャンピオン... 私たちはチャンピオン!!!!!
- 2025浅草サンバカーニバル「インペリオ」のテーマ&楽曲を紹介
インペリオ・ド・サンバ https://imperiodosamba.tokyo/ テーマ:Zico! O Galinho de Quintino E O Pais do Futebol! 『ジーコ!ガリーニョ・ジ・キンチーノ、サッカーの神様!』 サンバ・ヂ・エンヘード: シノプス: 歌詞:
- 2025浅草サンバカーニバル「セレージャ」のテーマ&楽曲を紹介
フロール・ヂ・マツド・セレージャ https://cereja.jp/ テーマ:「不死鳥 − 今ここに蘇る、復活 −」 サンバ・ヂ・エンヘード: https://cereja.jp/2025asakusa シノプス: 焼けつくような夏の空の下。 私たちは、あの日の悔し涙を忘れない。それでもサンバは止まらない。魂が踊りたがってる。 壊れそうな心を、リズムが繋ぎ、仲間の声が燃やしてくれた。 灰の中から蘇るのは――そう、不死鳥。 何度でも立ち上がる、強く、美しく、そして鮮やかに。 私たちフロール・ヂ・マツド・セレージャは、今年、まさに「復活」の物語をサンバで唄います。 響け、力強いバテリアの鼓動。 舞え、情熱の羽根をまとうダンサーたち。 輝け、私たちの願いと誇りを込めた衣装たち。 2025年、浅草の空に真っ赤なフェニックスが舞い上がる。 これはただのパフォーマンスじゃない。これは、私たちの叫びであり、誓い。 何度でも蘇る。立ち上がる。それが――セレージャのサンバだ!!! 歌詞: https://cereja.jp/2025asakusa
- 2025浅草サンバカーニバル「グローリア」のテーマ&楽曲を紹介
G.R.E.S. Acadêmicos da Glória (グローリア) http://samba-gloria.com/ テーマ:『開拓者たち PIONEIROS』 サンバ・ヂ・エンヘード: シノプス: 今から100年以上前の1908年、自分たちの夢と希望を抱きブラジルへ渡った日本人移民たちが幾多の苦難を乗り越え荒野を開拓し豊かな農園を作りブラジル文化に溶け込み成功していった、そんなパイオニア精神豊かな日本人達を称えます。 今年はブラジル国交樹立130周年という記念すべき年。 遥か遠き地にありながら、ここまで友好関係にありサンバを楽しめるのも、先人の開拓者たちのおかげです。 そんな日本人達に敬意をこめたエンヘードです! 歌詞: